駄菓子屋の店先には、子どもたちの夢とワクワクが詰まっていました。
数十円で買える小さなお菓子には、それぞれ独特の味や工夫があり、友達と分け合ったり、くじを引いたりする楽しさもありました。
しかし、時代の移り変わりとともに、多くの駄菓子が姿を消してしまいました。
本記事では、昭和から平成にかけて人気を博したにもかかわらず、今では「もう売っていない」駄菓子を5つ厳選して紹介し、その背景を振り返ります。
カットよっちゃん(小袋版)
酢漬けイカの独特な酸味で人気だった「よっちゃんイカ」シリーズの一つで、小袋サイズの「カットよっちゃん」は、駄菓子屋定番の味でした。
酸味と噛みごたえの魅力
「カットよっちゃん」は、一口サイズのイカを甘酸っぱいタレに漬け込んだ駄菓子で、噛めば噛むほど味が広がるのが特徴でした。
子どもでも買いやすいサイズと価格が魅力でした。
小袋タイプが消えた理由
現在も「よっちゃんイカ」は販売されていますが、昔の小袋タイプの「カットよっちゃん」は生産終了となっています。
健康志向の高まりや販売形態の変化により、駄菓子屋スタイルでの販売が減ったことが要因とされています。
懐かしさを求める声
SNSでは「昔の小袋が懐かしい」「駄菓子屋でよく買った」といった声が多く見られ、今なお記憶に残る駄菓子の一つです。
ぺろぺろキャンディ(駄菓子屋版)
今でも棒付きキャンディはありますが、駄菓子屋で数十円で売られていた「ぺろぺろキャンディ」は姿を消しています。
鮮やかな見た目と長持ちする甘さ
カラフルな渦巻き模様で、手に持つだけで楽しい気分になれるキャンディでした。
大きさも子どもにはちょうど良く、長い時間なめ続けられるお菓子として人気でした。
消えた背景
駄菓子屋の減少に伴い、低価格のぺろぺろキャンディは採算が合わなくなり、多くのメーカーが生産を終了しました。
現在はキャラクター商品や大型スーパーで売られる高価格帯のキャンディに取って代わられています。
思い出の象徴
遠足のおやつに選んだ人も多く、「駄菓子といえばぺろぺろキャンディ」と語る世代も少なくありません。
ドンパッチ
口の中でパチパチと弾ける食感が楽しい「ドンパッチ」は、1980年代から1990年代にかけて爆発的に人気を集めました。
驚きの食感
細かな粒が炭酸のように弾け、子どもたちに「食べる花火」と呼ばれることもありました。
味はソーダ、コーラ、グレープなどが定番で、見た目も鮮やかでした。
生産終了の理由
一度は販売終了となりましたが、その後復刻した時期もありました。
ただし現在は再び市場から姿を消しており、入手困難になっています。
需要の減少や原料コストの問題が背景にあると考えられています。
今も根強い人気
「懐かしい駄菓子ランキング」では常に上位に入り、大人になっても忘れられないお菓子として語られています。
ラムネ瓶チョコ
小さなガラス瓶風のプラスチック容器に、カラフルなチョコが入った駄菓子です。
瓶を振って取り出すワクワク感が子どもたちに人気でした。
遊び心あふれるデザイン
中身よりも容器のユニークさで人気を集めたお菓子でした。
食べ終わった後に容器を小物入れに使う子どもも多く、思い出深いアイテムとなっています。
消滅の背景
容器のコストや安全基準の変更により、次第に見かけなくなりました。
現在は同様のコンセプトを持つお菓子は存在しますが、当時の「ラムネ瓶チョコ」は販売終了しています。
ノスタルジーの象徴
「駄菓子屋の宝物」と呼ばれたほどで、見つけた瞬間に心が弾む存在でした。
プチプチ占いチョコ
カラフルな小さな粒チョコがシートに埋め込まれており、取り出すと占いの結果が出るというユニークなお菓子でした。
占い遊びとしての魅力
食べるだけでなく、友達と占いを楽しむことができるため、コミュニケーションツールとしても人気でした。
結果に一喜一憂する光景は、駄菓子屋ならではの風景でした。
消えた理由
大量生産が難しかったことや採算性の問題から次第に市場から姿を消しました。
現在は類似品もほとんど見られません。
思い出として語り継がれる存在
「当たるわけがないのに夢中になった」という声も多く、子どもたちの遊び心を刺激したお菓子でした。
まとめ

駄菓子は単なるお菓子ではなく、子どもたちの思い出や文化の一部を形作ってきました。
今回紹介した「カットよっちゃん(小袋版)」「ぺろぺろキャンディ(駄菓子屋版)」「ドンパッチ」「ラムネ瓶チョコ」「プチプチ占いチョコ」は、今では手に入らないからこそ特別な存在感を放っています。
時代の変化とともに姿を消しましたが、これらの駄菓子は昭和から平成を生きた子どもたちにとって、忘れられない記憶の一部として残り続けるでしょう。
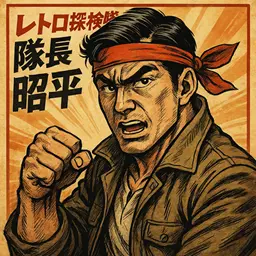
カットよっちゃんは連続で5回「あたり」がでたことがあるぞ!!



コメント